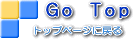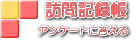|
|
|
|
|
|
YANAPY's HomePage TOP >> 北海道移住 >> 薪ストーブの導入
2010年 5月30日公開
我が家で薪ストーブを導入しようとしたきっかけは以下の通りです。 地元で生まれたエネルギー源を使う当地をはじめ北海道には森林が多く木がたくさん生えています。これだけ木が多く生えているのにどうしてそれを使わずにわざわざ何千キロも離れたアラブの国から石油を運んできて燃料にするのでしょう。 そうした素朴な疑問からです。 2008年の石油の異常高騰ではそうした疑問をますます感じました。 世界の一部の金持ちのマネーゲームのために生活物資となった石油の値段が振り回され、暖房への依存度の高い北海道の家庭はもちろん、北海道の経済が大きな打撃を受けました。 かねてから石油資源の枯渇さえ噂される中、地元で賄えるエネルギーを活用する方法を身につけておく必要があるのではないでしょうか。 環境への配慮薪など木質エネルギーは環境によいとされています。環境対策として二酸化炭素など温室効果ガス削減が叫ばれる中、薪など木質エネルギーはカーボンオフセットの論理で二酸化炭素排出はゼロとみなされます。 と書けば小難しいですが、要は木は植えれば再生するし光合成で二酸化炭素を吸ってくれるので環境にやさしいということです。 停電しても暖房は確保できる薪ストーブは薪さえあれば暖が確保できるもっとも原始的な暖房方法です。さまざまな暖房がありますが、その多くは何らかの形で電気を使用しています。ということは停電すると使用できないということです。 停電すると暖房以外にも日常生活の様々な面で支障が出ますので電力会社もそうした事態を避けるよう最大限の努力はしてくれてはいますが、台風や吹雪など自然災害時には特に地方ではどうしても発生する場合があります。 薪ストーブがくれるやすらぎもっとも原始的な暖房方法である炎が自然なやすらぎを与えてくれます。暖房の熱源は数ありますが、その中でも薪ストーブは体の芯まで温まる暖房だと言われます。 灯油ボイラーと併用完全に薪ストーブのみではなく、灯油による温水ボイラーと併用する形にしました。気温や時期などの条件を考慮しながらより燃費のいい組み合わせを考えていく構想です。 薪ストーブは不在時は管理できないのでそういう時の温度管理は灯油ボイラーにしてもらいます。 鋳鉄製薪ストーブを採用機種については、高気密住宅にも対応できる外気導入機能付きのものを中心に検討しました。その結果、ダッチウェスト社製のエンライトスモールを採用することとしました。  小型で燃費が良いことが我が家の使用実態に合うものと考えました。また薪ストーブ導入がはじめてということもあり定評のある機種を専門業者に施工してもらえるのもメリットです。
小型で燃費が良いことが我が家の使用実態に合うものと考えました。また薪ストーブ導入がはじめてということもあり定評のある機種を専門業者に施工してもらえるのもメリットです。鋳鉄製のストーブは鋼板製より最初の立ち上がりが遅いのではないかと心配もしましたが、実際に使ってみるとそうでもなく、順調に着火すればまわりから暖まってきます。 短時間で室温をあげたい時や、暖房の前で暖まりながらゴロ寝したい時など、パネルヒーターではできない仕事をしてくれるのは期待通りです。 薪ストーブもいいことばかりではありません。導入してみてわかる課題があります。 新築住宅は吸気不足薪ストーブは燃焼に酸素を使いますが、近年の気密の良い新築住宅では吸気不足が起こることがあります。また現在の新築住宅では24時間換気の設置が義務づけられており、24時間換気や換気扇等を使うと家の中が負圧になります。 この結果、特に着火までのストーブや煙突が冷たく上昇気流のドラフトが確保できない時に、気流が逆流し、この状態でストーブに点火すると煙が逆流してきます。 現実に我が家の薪ストーブでも煙突から部屋内部に常に風が吹いており、最初慣れない頃は煙が逆流し火災報知器を鳴らしてしまったこともあります。 薪ストーブの中には部屋の空気を使わずに屋外から直接空気を入れる外気導入機能のついたものがあります。 我が家でも外気導入機能付きのものを採用していますが、これでも吸気不足が起きるとの業者の説明があり、現実に着火時には吸気不足が起きています。 我が家で吸気不足が起きる場合の対処ですが、 1.24時間換気や同時吸排気を切る。 2.それでダメなら窓をあける。 (うちにはガラリがあるのでそちらをあけています) を着火から充分なドラフトが起きるまで行い対処しています。 薪の確保薪の確保も決してラクなことではありません。実際に導入した住宅でも薪の確保に苦労している家は多いようです。 ストーブ店から薪を買う方法もありますが値段的にはそれなりにします。 ネット上などで薪を扱う店舗もいくつかありますが値段的にそれなりにするのは同じです。 またいずれにしても遠方であれば送料が発生し、重量もかさもあるものなので結構な値段です。 ホームセンターでも細々と売っていますが、1回使ってみるくらいならまだしもあれだけで冬は越せません。値段も本格的に使うことを考えるとけっこうな値段です。 自分で生木から薪を作る方法もあります。 ただ、山でも持っているなら別ですが、それでなければまず生木を買うのが大変です。 伐採業者などは個人が使う小口ではなかなか売ってくれません。手間がかかるからです。 生木を買えたとしても大変重たいです。人力や軽トラぐらいでは運べません。 保管場所も必要です。樹皮や木くずなどで結構汚れます。 また薪の保管場所も必要です。 1シーズン分の薪をストックするのに結構場所は必要です。 さらに薪作りのための用品も必要になってきます。 薪を購入したとしても焚き付け用など太さを調整するために斧が必要になります。 自分で薪を作るならチェーンソーなども必要になってきます。木を運ぶのにトラックもいります。 うちの場合ですが、  生木から薪を作ってみました。
生木から薪を作ってみました。地元のつてで何とか立派な生木を入手し、建設会社のユニック付のトラックで運んでもらい、義父が借りている山の中の作業場で義父の道具で玉割り・薪割り作業をし、義父のトラックで運ぶという形になりました。 この通り、自分ひとりの力だけでやるには厳しいものがあり、いつまでこの方法ができるかなぁ?といったところです。 購入した薪について。 生木から作ったものは乾燥が必要なため今年度のものにはならないので、今年度の分は別途購入しました。 地元に薪を作っている林業者があったため、結束無し、土場からトラックで自分で搬出という条件でトラック1台いくらという形で市販の薪よりは安く入手することができ、義父のトラックを借りて搬出しました。 間伐材を使用しているので見た目は必ずしも立派なものではないという事前説明は業者からありましたが、地元で生まれる資源を有効利用したいという我が家の趣旨には見事に適合しています。 これでもひと冬を薪ストーブだけで越そうとするとトラック3〜4杯分は必要になると思われます。手間も費用もバカになりません。 コストだけで言うなら割にあわない完成品の薪の値段は使用量も考えると決して安いとは言えないです。薪を自前で作るにしても、用具や手間を考えると安くはないのは同じです。 山や用具をすべて自前で持っていてヒマもあるというならまだしも、コストだけで言うなら灯油が値上がったとしてもまだコスト的には灯油の方が優位でしょう。 うちの現状で薪代だけの話で言っても、灯油が200円/lぐらいにならない限りはコスト的には灯油の方が優位だと思われます。 2008年の原油高騰時には薪ストーブが売れたという話もあったようですが、コストだけで言うならどうかなぁ?と思うところがあります。自分の山で木が採れるならまだ話は別ですが。 本当に環境にやさしいのか?薪をはじめとする木質エネルギーは再生可能という意味では地球にやさしいエネルギーであると書きました。でもそれは果たして本当にそうでしょうか?現状の林業は決して木こりさんが斧で木を切っているわけではなく機械を相当使用しています。また木の運搬も重機ですし、生木からの加工にも機械を使用します。業者から購入する薪は薪割り機を使用していると考えて間違いないです(手作業なんかでやったら体を壊します)。 自分自身、生木からの薪作りや運搬をしながらこのために結構化石燃料も使用しているなぁと感じながら作業をしていました。 それでも薪ストーブが良いところは、薪ストーブならではの楽しみがあるところです。 薪作りや運搬・積上げなどの薪の準備や、煙突やストーブの掃除など手間がかかる部分も多いですが、その一方で薪ストーブの質感や炎が生み出すインテリア性など現代の進化した薪ストーブは私たちを楽しませてくれる要素もあわせもっています。 手間も冬の風物詩として楽しめるのであれば、薪ストーブは現代の文明社会が忘れかけている人間のもともとの姿を思い出させてくれるのではないでしょうか。 子どもと薪ストーブ小さな子どもがいる家庭では薪ストーブは危険と考えるようです。確かに大変危険です。薪ストーブの外部は250度を超えますし、うっかり火室を開けようものなら火事の原因にもなりかねません。 ただ子どももやはり動物的に火は危険と思うようです。何でも過保護にせず危険なものは危険とわかってもらうことも必要かもしれません。もしどうしてもやんちゃな子どもで心配ならストーブガードでも設置されてはいかがでしょうか。 うちも小さい子どもがいますが、灯油ストーブの頃も含めて火のついているストーブに手を出して怪我をしたことはありません。普段からよく言い含めていますし、ストーブがついていないと手を出しますがついていると不思議と手を出しません。ストーブガードは使用していませんが今のところやけど等の事故はありません。もちろん親が注意して見ていることも必要です。 薪ストーブで結露?最近の高気密住宅では結露の心配は少ないのですが、結露の心配がないように暖房計画も配慮されています。だから窓の下には温水暖房などパネルヒーターが配備されていることが多いです。ただ薪ストーブを使用すると集中熱源になるので熱源から遠い窓で小規模な結露が起きることがあります。我が家でも実際にありました。パネルヒーターの動作中には起きないので薪ストーブの使用によるものが大きいのかと思います。 もっとも家の間取りや加湿の状況など使い方によってもいろいろだと思います。 比較表
実際はどうなのよ?我が家は薪ストーブと温水暖房を併用し、両者の特徴を活かして利用すべく試行錯誤中です。導入初年は前半は薪ストーブを主体に使い温水暖房を極力抑制してみました。 しかし薪の減りが早く尽きる懸念が出たため後半は休日のみの稼働としました。そうしたら今度は薪が余ってしまいました。 また火をつける手間を惜しんで火を絶やさないようにしたため有効活用という点では疑問が残ることもありました。 2年目は主に帰宅後の時間帯に部屋の温度をあげるために使用し、夜間は消火、朝は温水暖房を使う方式を取り入れ、現在データをとっています。 参考までに、前住んでいた教員住宅と、現在の住宅との灯油使用量の比較グラフです。 給油量を日数で割ったものを1日あたりの灯油使用量として、毎年の平均値をグラフにしてあります。 どちらの住宅も(機器は全く異なりますが)給湯と暖房に灯油を使用しています。 床面積はおよそ2倍、通常の居住空間は2割程度増えていますが、灯油の使用量はほぼ変わらず年間約1,600リットル程度となっています。薪ストーブの効果なのか、新住宅の断熱の良さなのか分析はこれからです。 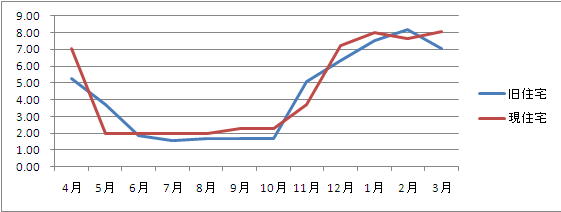 ※給油サイクルが違うため単純比較は困難です。新住宅は5〜9月まで無給油なのですべてが平均され暖房を使う5月とかは低く使わない7・8月などは高くでがちです。
※給油サイクルが違うため単純比較は困難です。新住宅は5〜9月まで無給油なのですべてが平均され暖房を使う5月とかは低く使わない7・8月などは高くでがちです。 |